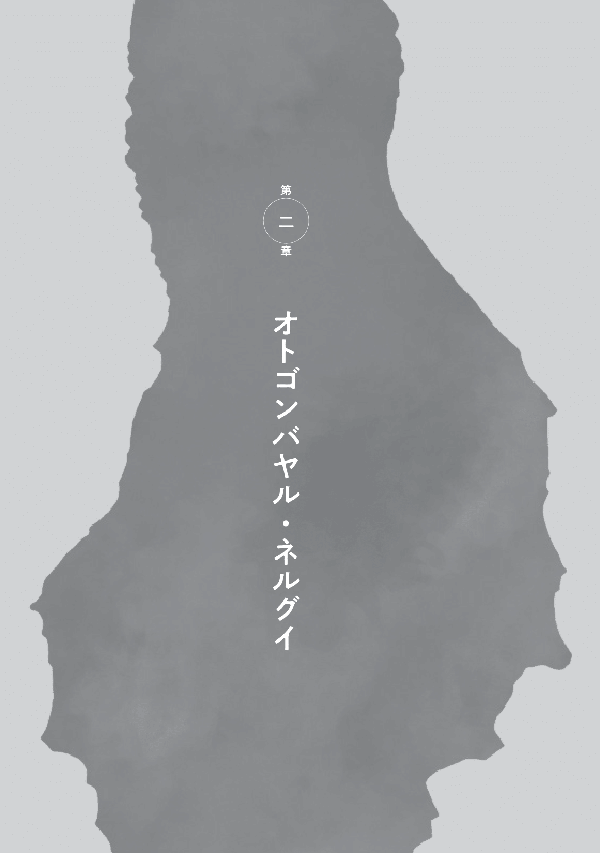
オトゴンバヤル・ネルグイ
ウランバートルの中心を東西に縦断するエンフタイヴァン通りは、十二月のクリスマスシーズンを迎えたせいもあり、激しく渋滞していた。
歩いた方が早い、と諦めたオトゴンバヤル・ネルグイは、トロリーバスを降りると、スフバートル広場から三ブロックほどの日本食レストランへと徒歩で向かった。
モンゴルの冬はマイナス二十度を超えることもしばしばで、今日の外気は凍えるような寒さだ。肉厚のダウンを着込み、毛糸の帽子に手袋、といった出で立ちでも、まだ十分とはいえない。道行く人々も言葉少なで、彼らの口から漏れる吐息は、薄暮の中、驚くほどに白い。
大通り沿いには東欧風の高層アパート、キリル文字の看板で飾られたカフェやレストランが賑やかに立ち並び、雪で真っ白な歩道と平行して、動かない車の列が延々と一直線に伸びている。
ネルグイはそれを横目に、氷のように固まった歩道をショートブーツで踏みしめながら歩いた。
なぜ叔父は自分を呼び出したのだろう。
いつもなら事前に用件を伝えてくるはずなのに…
彼は、黒いブーツの足先にこびりついた真っ白な雪を見つめながら考えた。
ネルグイの叔父ドルジは、大手雑誌社の編集長である。
同族の中ではつとに成功者として知られ、父母を早くに亡くした彼にとっては常に威厳のある父のようでもあり、時には愛情あふれる母のように接してくれる頼れる存在だ。
十六の頃、家計を支えるために職を探す際にも、彼はネルグイに力を貸した。友人である清掃管理業の社長に働きかけ、日本人学校の清掃員としての働き口を見つけてくれたのである。
この就職はネルグイの転機となった。
もともと彼は小学校から日本語を第二外国語として選択していたこともあって、日本や日本人への関心は高かった。ゆえに、彼の喜びは一通りではなかった。
なにしろ、憧れだった日本の生活スタイルや文化に日々触れることが出来るのだ。
一年も経つと、生来の愛想の良さもあって、児童や教職員との交流も格段に増え、彼からの図書室の使用の申し出についても学校側は快く応じた。
やがてネルグイが、校内にある日本語の本を読み尽くしたころ、ある教師から学校新聞への寄稿を頼まれた。
「日本とモンゴルの子供たち」
素人離れしたそのエッセイは、たちまちのうちに評判となり、その噂が自然にドルジへと伝わった。
「児童向けの記事依頼が何本かあるんだが、興味があるなら、ちょっと、やってみないか?」
出来上がった原稿のクオリティを見て、ドルジの目の色が変わった。これをきっかけにして、彼はネルグイに次々と仕事を持ち込むようになった。
それが今や、モンゴル有数のフリーランスライターとなるのだから、人生とは分からないものだ。
すべてドルジのおかげ。
命の恩人といえるドルジのためなら…
その覚悟を彼は常に持っていた。
それになによりネルグイはドルジの大らかで豪快な性格が好きだったのだ。
ホテル二階の和食レストランののれんをくぐると、店内はテーブルを竹垣のついたてで仕切った居酒屋のような気取らない雰囲気で、まだ早い時刻ではあったが、既に多くのモンゴル人で満席である。
ネルグイは店内の四人席に案内されると、そこにはすでにどっかりと重い体を椅子に預け、馴染みの日本酒で杯を傾けるドルジがいた。
ネルグイに気づくと、ドルジは、よく来た、と言わんばかりに両腕を広げ、目尻を下げて彼を迎えた。
「どうだ? 最近?」
ネルグイはにこやかに応じつつも、いつもなら遅刻するはずの彼が、と、今日の呼び出しがただならぬ意味を持つことをすぐに悟った。
「この前依頼したタウン情報誌の仕事。あれはな、なかなか好評だったぞ。やっぱり、日本語でネイティブ並みの記事が書けるってのが、お前さんの強みだからな」
「そぉ? 気に入ってもらって良かったよ。僕にとっても町の最新スポット巡りも出来たしね。正直、これでお金もらっていいの?って感じだった」
ネルグイはおどけた。
ドルジは、ネルグイが到着する前から相当飲んでいたのであろう、大きな丸顔の頬は紅を差したように赤い。
店員を招き寄せて追加の注文をすると、彼はさっそくネルグイにグラスを持たせ、追いつけ、とばかりにその縁からこぼれるくらいの酒を注いだ。
ほろ酔い気分になると、ドルジが決まって語りだすのが、草原の日々の思い出である。
「お前の父さんはそりゃあ強かったぞ。男前だったしな。俺の小さい頃のモチベーションっていったら、兄をどうやって打ち負かしたらいいかっていう気持ちが一番だった。けど、兄さんは相撲、乗馬、将棋、おはじき、羊飼い、肉の捌き方、すべてにおいて上。どんなに努力したって勝てねぇんだから。…一度だけシャガーンのおはじきで俺が勝ったときなんて、兄さんは不機嫌でねぇ」
ドルジは乾いた声で笑った。
叔父が言うまでもなく、父はネルグイにとっての誇りだった。
夏のある日、ネルグイがウランバートルの小学校の寄宿舎から草原の移動式住居、ゲルに戻っていたときのことである。
そこで目にしたのが、放牧によって野生化した馬を手なずける「荒馬慣らし」だ。
「よく見てて。ドルジおじちゃんは追い込みの名手だから」
母の視線の先には、ラクダのこぶのように連なる丘陵の裾野に広がる平原で、土埃をあげながら逃げ惑う数十頭の蒙古馬がいた。
その群れの中心には、身長の倍はあろうかという馬追い竿を手にして、家畜小屋の前に巡らされた手製の牧柵の中へと彼らを追いやるドルジが見えた。
竿を上手に振りながら、一匹々々の動きをしばらく見極めていたドルジは、やがてひときわ体が大きい暴れ馬に狙いを定めると、いとも簡単に輪投げのように竿の先端の皮ひもをひらりとその首にかけた。
親戚の男たち二人も、その馬に一斉に取り付き、力任せに押さえ込もうとするが、如何せん、馬も激しくいななきながら後ろ足を跳ね上がらせ、人の意になるものか、と必死である。
その様子を静かに見守っていた中折帽に渋茶の民族衣装のデールを着た父は、今だ、と、男たちの間に滑り込むと、手綱を引き取り、軽々と暴れ馬の背に飛び乗った。
だが、馬はいよいよ嫌い、身体をくの字にして彼を振り落とそうとする。
父の体は鞍上で鞠のように跳ね上がり、そのたびにネルグイの心臓は縮み上がった。
おののく彼の心を見透かしたかのように、父は、未だ馬がたてがみを振り回して静まらないというのに、片足を外して一方のあぶみに全体重をかけ、手綱を張り、まるで奇術師のように身を反らせ、茶目っ気たっぷりにネルグイを見た。
ネルグイは息を呑んだ。
しかし、それから後の光景は、彼をさらに驚かせるものだった。
なんと、先程までとても手がつけられなかった馬が、鼻から荒い息を吐き出しながらも、いつのまにか嘘のように大人しくなっていくではないか!
父は、馬が落ち着いたのを見計らうと、ようやく帽子の下に満面の笑みを浮かべ、悠然とその場で馬とともにくるりと回った。
駿馬は男の飾り。
その夏、最も荒々しい馬を掌中に収めた父を見てネルグイは心底そう思えた。
「しかし」
ドルジは表情を変えてつぶやいた。
「お前の母さんのことは俺らにとっても最大のショックだった。面倒見もよく、一族からあれだけ愛されていた人を俺は知らない。何よりドルマーほど美しかった人を、俺は知らない」
苦虫をつぶしたように、また、運命に喧嘩を売るかのようにいまいましげに語りながら、ドルジは一気に飲み干した杯をとん、とテーブルにぶつけた。
母の存在。
そうなのだ。父の誇りを誇りたり得たのはネルグイの母がいたからだった。
ネルグイにとって忘れられないのは、夏営地から秋営地へとゲルを畳んで家族が大移動する際、先頭に立って導く馬上の母の姿だ。
日頃は家畜の世話や酒とチーズづくり、洗濯、掃除、と忙しい母なのだが、いつもこの日だけは違った。
前方には遥かに霞む薄墨色の山々がいくつも折り重なり、なだらかな草原は果てしなき緑の絨毯となってどこまでも続き、淡紫色のマツムシソウが霞のように大地に拡がっている。
ハーブの清らかな香りが馬を進めるたびに鼻から頭頂へと気持ちよく突き抜けていく。
父は数百頭の家畜の群れを馬上で見守りながら、ゆっくりと進み、姉のツェツェグとネルグイも同じく馬を操り、一行は四キロほどの行程を扇状になって目的地へと向かった。
荷物を背負う二頭の駱駝を従えながら、冴え渡る乳青色の大空にくっきりと浮かぶ母の背中を、ネルグイは頼もしく何度も見返した。
もうすぐ二ヶ月の夏休みを終え、寄宿舎に戻らねばならない。この時間がいつまでも続いてくれたら、と彼は願った。
「町に帰ったらしっかり勉強なさい。旧正月の冬休みには新しく身につけたことをわしらに教えられるように、な」
別れ際に、父はそう諭した。
父母や祖父母に見送られながら後ろ髪を惹かれるように親戚の車に乗り込み、ゲルを後にした時のことを彼は昨日のように克明に覚えている。
そんな家族としての時間は、約束されたものとして永遠に続くかと思われた。
あのゾドと呼ばれる冷害が来るまで。
==============================================
零下五十度という記録的なゾドをさらに深刻にしたのは、前年からの干ばつだった。
いつもなら冬越しのために草を食み丸々と肥え太らねばならない時期に、家畜達はあばら骨を見せたまま冬に突入せざるを得なかったのだ。
そこに猛吹雪が襲った。
わずか数メートル先も見通せない叩きつけるような雪の中、羊やヤギは為す術もなく大雪の中に埋もれていく。父母や祖父母が懸命に雪を掻き出しては励ましながら掘り起こすも、焼け石に水だ。
三百頭を超えた家畜は次々と立ったまま息絶えた。
さらに悪いことに、酷寒の中で作業を続けた祖父が低体温症となって倒れ、なんとか父が力ずくで引きずってゲルに運び込んだものの、しばらく熱い熱いと苦しんだあげく、やがて無反応となり、動かなくなった。
翌朝は昨夜の吹雪が嘘のように真っ青に晴れ渡ったが、家族に残されたのは無情にも、祖父の遺体と、ほぼ全滅に近い家畜の死骸のみであった。
父の決断は早かった。
生き残った家畜を親戚に託し、ゲルを畳むと、首都ウランバートルから車で二十分ほどの丘陵地に居を移し、とにかく市内で職を見つけよう、という運びになった。
ただ、父はもともと寡黙な方であったが、この移住を境にますます語らなくなっていく。
見つからない定職と工事現場の重労働。そして報われない賃金。
いきおい、父は酒に溺れた。
あれはモンゴルの歓喜の夏を祝う祭り、ナーダムを翌月に控えた六月の夜のことだ。
父は前触れもなく、突然路上で倒れた。
死因は密造酒の過剰摂取によるメタノール中毒。
一族にとって仰ぎ見る存在であった父が、こうもあっけなく地上からいなくなるものなのだろうか。
ネルグイは病室でやせ細った父の胸にそっと手を置いた。
信じられないほどの冷たさだ。
ネルグイの脳裏には、なぜか、幼い頃、父の心臓の熱い鼓動に耳を当てた記憶が鮮明に蘇った。
とめどなく流れる涙を拭きもせず彼は立ち尽くしていた。室内には母の絶望に近い叫びと、咽び泣く妹の声が何時までもこだました。
==============================================
「おい、聞いてる?」
ドルジは焦点のあっていないネルグイの目を覗き込んだ。
途端に現実に引き戻された彼は、ごめん、ちょっと昔のことを思い出してて、と、照れくさそうに頭をかいた。
「ところで」
ドルジは自らの昔話が一段落すると、今度は、これまでの鷹揚とした態度は嘘だったかのように神妙な顔をした。
「今日呼んだのは他でもない。実はな、お前の力が借りたいんだ」
ドルジの眼は凄みを帯び、いつも以上の熱量を感じる。
「実は、イギリスで海洋調査会社をやってる俺の友人がいてな。その彼から連絡を受けたんだが、お前、日本の福岡というところ知ってるかい?」
「ああ、相撲の大競技会が毎年あってるとこだよね」
「うん。その通りだ。で、その福岡なんだが…彼によるとその福岡にある湾の海底には沈没船が埋まってて、そこにごまんと財宝が積まれてる可能性が高いって言うんだよ」
「財宝?なんか夢のような話しだね…騙されてるんじゃないの?」
「うん。確かに信じがたいことだが、決してありえない話しではないんだ。
というのもな。モンゴル帝国が十三世紀に日本を攻撃したことは知ってるだろ?その際、彼らはまず九州島を手中に納め、その後日本全土を占領するのが目的だった。
戦闘は当然、長期に渡る。で、何が必要と思う?
金だよ! 金銀を始めとした資金だ!
が、その後の侵攻の結末は、と言うと、折からの強風で帝国軍の艦船は壊滅的な打撃を受け、命からがら帰国したってのが定説になってる。つまり、難破船が湾から見つかる可能性は、極めて高いんだ…。
とりわけ俺の友人が着目しているのが、湾の入り口を塞ぐように位置している島だ。ノコノシマというらしい。この周辺海域であれば、堆積した泥の下から沈没船を探すのは容易だ、と言うんだよ」
「で、僕に海に潜ってこい、と?」
ドルジは笑った。
「いや、そうじゃない。友人から依頼されたのは、な。数ヶ月にわたってその島の事前調査が出来る人物がいないか、ということだった。
実際に沈没船を引き揚げるとなると大ごとだし、まず日本との権利関係が整理できるかどうかさえも分からない。投資効果が明らかでない以上、金は掛けられないってことだ。もちろん通訳もつけられないし、安宿で我慢してもらわないといけない。そうなると依頼できる人物は自然と限られてきてね…」
ドルジはいくぶん申し訳なさそうに眉を寄せ、ネルグイの反応を伺った。
「だから僕なのか」
ネルグイは合点したように頷き、くすくすと笑った。そして間髪をいれず答えた。
「分かったよ。もともと僕は記者だし、ラップトップと携帯さえあればどこでも仕事は出来るから。そして何より長年夢だった日本での生活を満喫できそうだし」
あまりに急な快諾にドルジは目を剥いて驚いたが、次の瞬間にはもう手を打っていた。
「そう来なくちゃ」
ドルジは、子供のように満ち足りた表情を見せると、空になった徳利の首をつまみ、ネルグイの眼の前で遊ぶように揺すった。
「おもしろくなってきたぞぉ。さぁさ、今日は、どんどん飲んで、食ってくれ」
二人の目の前には、まだ食べ終えていないというのに、次々と刺し身やコロッケ、唐揚げなどが所狭しとテーブルに置かれていく。
ネルグイは思った。
これでしばらくはドルジを通じて父や母ともつながることが出来る。
たとえそれが記憶の中だけの父母であったとしても…
夜のウランバートルの町は渋滞がいくぶん和らいできたものの、まだ車は車間距離も十分に空けずに、連なるように上り下りともにゆっくりと進んでいる。
際限なく湧き上がる真っ白な蒸気が、幾多のテールランプに赤く照らしだされては虚空へと消えていく。
それは、まるでどこか知らない異世界の入口へと車列が向かっているようでもあった。