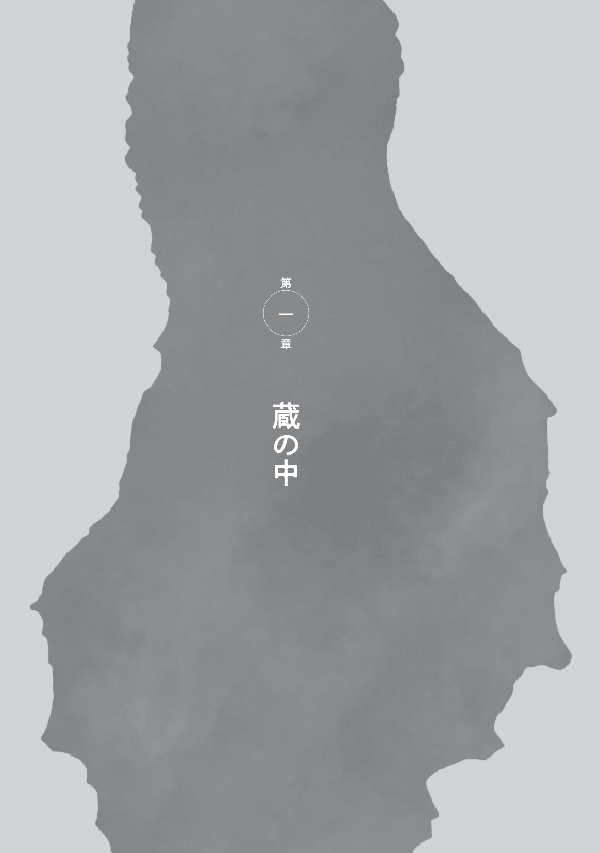
蔵の中
「何で今なのよ!」
「今こそお父さんの力が必要だって時に!」
眉間にしわを寄せて当たり散らす母の声を、慎治はただ黙って聞いていた。
妹の未來は、というと、まるで人ごとのように病院前の歩道から曇った空を見上げている。
母の玉江が不安に感じるのも無理はない。
慎治と未來が未だ私大に通っているというのに、駅前に大手が進出してきてからというもの、家業である不動産の収入は先細りする一方だった。
何しろ小さな町だ。顧客のパイは限られている。
父としても、事態を打開するには、柔軟な発想が出来る新しい世代にバトンを渡すしかないことは分かっていた。
ゆえに、慎治の卒後の実習先についても、父は早々に手を回し、友人の会社から既に内諾を得ていた。
そして、いよいよ事業のノウハウを実地で教えようかという段になって、父が通院している病院から突然電話があった。
父・丈一郎のがんを告げられた時の母のうろたえぶりは尋常ではなかった。子供たちもしばらくは母を交代で見守っていたほどだ。
が、とは言え、慎治には、母の気持ちを受け止めて慰めるほどの余裕もなかった。
父の真似はとても出来ない…
仕事であれ、家のことであれ、万事手抜ぬきをしない父を知っているだけに、自分がその後を継ぐかと思うと、慎治はそのたびに挫けそうになった。
父の手帳を慎治は一度だけ覗いたことがある。
カレンダーにはびっしりとスケジュールが書き込まれ、業者への個別の支払額までもが日付順に克明に記されていた。
…あり得ない…
父の几帳面な性格は、のんびりとしてマイペースな慎治とは何から何まで真逆だった。
「お前は静か過ぎる。いるのかいないのか、はっきりしろ!」
居間の片隅で本に読みふける慎治を、父はよく叱った。よほど息子が頼りなく見えたのだろう。
慎治は童顔で小柄なため、よく女性と間違われた。それも父にとってはしゃくにさわるようだった。
兄弟で比較すると、父に似ているのはむしろ妹の未來で、身長も体格も顔つきも、こだわりがある性格さえもそっくりだった。性別こそ違えど、跡継ぎとしての資質は自分よりも備えているのではないか、時として慎治にはそう思えた。が、逆にそれがいまいましくもあった。
「まったく…今日は病院の駐車場も満杯で入れないし、入院手続きに時間はかかるし、暑いし、で、さんざんだねぇ」
有料パーキングに着くと、母は未だに気持ちが収まらないのか、まだ車のドアの前でぼやいている。
知らんぷりをして慎治が車のドアを開けると、冬というのに中は驚くほどの熱気だ。
思わず慎治は顔をしかめ、パワーウインドウで四つの窓を全開にした。
車の後部座席に未來が身を沈めるや、彼女はバックミラーに映る慎治の目をのぞき込み、ぶっきら棒に言い放った。
「お兄ちゃんも大和家の当主という立場にいずれはなるんだから、いい加減、自覚しないと」
人の気も知らないで。
慎治は内心憤った。
分かってはいる、自分がしっかりしなければいけないことを。分かってはいるのだ。
しかし大学生活に何の意義も見いだせず、惰性で留年してしまった今の慎治にとっては、あまりに荷が重かった。
この五年というもの、授業受けるにも、これが家業の何に役に立つのか、と疑問ばかりが先立つ日々だった。そして、入学時に比して自分のどこが変わったかと問われれば、情けないことに、何も変わっていないとしか言いようがない。
将来の展望が見えない中、父の病状の悪化も重なり、慎治は、家のことを母や妹と語るのを極力避けるようになっていった。
片側三車線の大通りから都市高速道路へと向って連なる車の列は、事故なのか何かのイベントなのか、渋滞でぴくりとも動かない。
後部座席から未來がいらぬ世話を焼いて道順を指図し始めると、母も同調して言葉をかぶせてくる。
慎治は、あぁ、分かってるよ、と生返事しながら、左手でラジオのプリセット番組を検索した。
スピーカーからは落語や英会話などが流れるばかりで、お目当ての音楽番組は見つかりそうにない。
とうとう諦めた慎治は、前を走るタクシーの屋根上の表示灯をぼんやりと眺め、後ろに座る二人から見えないように隠れて嘆息した。
二
父の入院時の検査が一通り終わり、治療方針の家族への説明などが一段落したころ、病院に見舞いにいっているはずの未來から慎治に突然電話がかかってきた。
父はこれまでも直接言いづらいことがあれば、度々妹をメッセンジャー代わりに使ってきた。
今回もそのたぐいか?
マナーモードのバイブが止み、着信履歴に妹の名前が表示されると、慎治はそう直感した。
授業が終わり、講義棟前のベンチに座ってさっそくLINEすると、お父さんが話したいことがあるそうよ、という案の定の返事である。
しばらくは憮然として空を見上げていた慎治だったが、やがて意を決したのか、明日の午後行く、とそっけない返事を返した。
慎治が翌日病院を訪れると、父の病室は、四人部屋から当初の希望どおり新館の特別室へと変わっていた。
恐る恐るスライドドアを引き、室内をのぞくと、病室の中央には電動ベッドで上半身を起こし、壁掛け型のテレビをぼうっと見つめている父の姿があった。
応接セットの二人掛けソファにはすでに未來が先客として座っている。
「おう」
入室してきた慎治を見つけた父は、少しほっとしたような明るめの声を上げた。
慎治はおもむろにリュックをソファのシートに降ろすと、病室の隅にスタッキングされた丸椅子をひとつ引き寄せ、浅く身を乗り出すように腰掛けた。
たわいもない世間話しがしばらく続いたが、数分も経つと二人の会話は途切れた。
沈黙の気まずさから、慎治は腕時計をちらちらと覗いたり、病室の中を見渡したり、とそわそわと落ち着かない動作を繰り返している。
やがて未來が、見かねたように、わざとらしく助け船を出してきた。
「あぁ、そう言えば、昨日電話で話したことなんだけど」
父の表情に一瞬、光が差したように見えた。
「お父さんがねぇ、家の蔵の整理をしてくれないかって言ってるのよ。大和家って、昔は大庄屋していただけに、指定文化財になるような品物が蔵の中にはゴロゴロしてるでしょう?だから、自分がしっかりしている間にケリを付けたいんだって。長男であるお兄ちゃんにはやっぱり一番に関わってもらわないと」
常日頃冷静な未來が頬を紅潮させて語る様を見て、これだったのか、と慎治はようやく合点がいった。
大和家はもともと現在の福岡県中南部に当たる筑前国・穂波郡花瀬村の大庄屋だった。
花瀬は当時、九州の幹線道路である長崎街道と商都・博多へと通ずる篠栗街道とを結ぶ結節点であると共に、北九州全域から集まった米やさまざまな産物を大阪方面へと輸送する中継基地でもあった。
この地の大庄屋として十一代目の大和四郎左衛門が福岡藩に取り立てられるや、家業は益々繁栄し、明治期には炭鉱経営に乗り出すなど、一族は栄華を極めた。
ゆえに、地元の郷土史家や博物館の学芸員にとって大和家の蔵はかねてより羨望の的で、再三調査を打診されていたのだ。
慎治にとって、蔵の記憶というものはほぼない。
思い出せるのは祖母と一緒に正月の汁椀とおとそ用の盃を取り出すために入ったときくらいで、暗がりへの恐怖とほこりだらけの室内を忌み嫌い、その後も好んで立ち入ろうとはしなかった。
むしろ、妹の未來の方が幼いころから蔵の中を遊び場にしていて、喜々として蔵に入っていく姿をみて慎治はいつも不思議に思っていたくらいである。
「すまんなぁ」
二人のやり取りを静かに聞いていた父がぼそりとはじめて口を開いた。
慎治は、日頃謝ることなどまったくない父が急に謝罪してきたことに面食らった。
「俺も蔵の整理については若いころから何度も挑戦してきたもんだ。…けどな。あの蔵の物は、四百年以上大和家が築き上げてきた歴史そのものだ。とても片手間で出来るような代物んじゃない。かと言って、専門家に丸投げするのも御先祖様に対して申し訳なくてな…やはり、身内の者ががっぷり四つになって関わって立派に整理するのが筋ってもんだろ? そう思わんか?」
いつもなら、父の自慢げな様子が鼻につき、聞き流しているところである。
が、ここ数週間、父が家の歴史に触れる時、そこには有無を言わせぬ迫力があった。
「それに、な。お前も分かっていると思うが、一番気がかりなのは、大和家と千利休の関係についてだ。
利休といえば、言わずとしれた茶の湯を大成させ、豊臣秀吉に寵愛され、現代でいえば副総理のような立場を務めた堺茶人の巨頭だ。
その利休が、うちの庭を設計した、という記録が残っている、というんだから!」
父は興奮して鼻の穴を広げた。
郷土史家からの情報とはいえ、この件は慎治も長らく半信半疑だった。
蔵を整理する中で、秀吉や千利休と我が家との関係を証明する何らかの書状や品々が出てくる可能性は確かにある。
が、家業のことだけで手一杯というのに、一族の歴史まで引き受けねばならないとは…
慎治の心はたちまちざわついた。
「一人で、とは言わない」
病室の床をじっと見つめている慎治の心を見透かしたように父が言った。
「俺の小学校以来の親友で毛利嘉宏君という男がいる。高校の社会科の教師なんだが、今は退職して趣味の歴史探索三昧だ。彼に相談したところ、喜んで手伝うと言ってくれてる。
お前も大学卒業前で色々と忙しいとは思うが、我々家族だけでなく、長年続いてきた一族に関わることだ。どうか、頼んだぞ」
父が慎治に物事を頼むときは受けることを前提で、全てお膳立てされてから呼び出されるのが常だ。
いつもなら沈黙し、せめてもの抵抗を示すところだが、今の父の前では…
慎治はわずかに頷きながら一瞬だけ父の顔を見ると、すぐに視線を泳がせ、病室の扉へと目を逸らした。
その姿をはたから眺めていた未來は、満足げに口元に微笑みを浮かべている。
しばらくすると病室の静寂とは裏腹に、廊下から配膳カートが行き交う音が聞こえ、やがて食膳を手にした看護助手が笑顔で現れた。
父が陽気に軽口で応じるのを見て、慎治は、ようやく病室の張り詰めた空気が破られたことにほっと胸をなでおろした。
帰り道、助手席で、全面的にバックアップするから、と嬉々として申し出る妹に、まんまと載せられた、と慎治は苦笑するしかなかった。
普段なら兄として皮肉の一つでも浴びせたいところだが、なにしろ、未來は、卒業後は博物館勤務を目指しているほどの筋金入りの歴女である。蔵の整理にあたっては、彼女の手を借りない訳にはいかない。
「博多駅で降ろして。見たい服があるの」
今後の調査の段取りについて語るだけ語り、軽やかに車を降りていく未來を、慎治は少々呆れながら見送った。
三
毛利嘉宏が花瀬町にある大和家の本家を訪れたのは、それから数日してからのことである。
駅まで迎えに行きます、という慎治の申し出を丁重に断り、最寄りのバス停を降りると、彼は一人大和家へと向かった。
なんでも、目的地に着く前から歴史調査は始まる、という彼独特の強いこだわりによるものだった。
ぼさぼさの白髪に厚手のジャケット、ネクタイを固く締めているせいで、銀縁メガネをかけた赤ら顔の額には、すでにうっすらと汗がにじんでいる。
「土地の氏神である花瀬宝満宮のそばの小高い丘のうえ…うん、あの時のままだ。何も変わってない」
鼻までずり落ちたメガネを直しながら、彼は独り言にしては大きすぎるほどの声を挙げた。
なるほど、行く手の高台には鬱蒼とした裏山の緑を背に、植栽の木々の間から堂々たる邸宅が見え隠れしている。
苔むした左右の石垣にはさまれた狭い急坂を、毛利は腹からずり落ちるベルトを直しつつ、息を切らせながら登った。
やがて門柱の向こうには風格ある平屋建ての母屋が現れ、その隣には白亜の蔵が見えた。
蔵をよく見ると、外壁の漆喰は手を触れれば今にも崩れ落ちそうで、至る所に亀裂が入り、ところどころ竹の下地が露出している。
母屋の前に広がる庭池には、飛び石が配され、悠然と泳ぐ鯉が見える。その奥には、まるで古老のような肌をしたムクノキが森のように茂り、木陰を作っていた。
感嘆して立ち止まった毛利は、蔵の壁に反射する庭池のゆらゆらとした光や、白壁を背にくっきりと咲き誇る紅梅に見入ったまま、しばらく時を忘れたかのように立ち尽くしていた。
慎治は自宅で毛利の到着を今か今かと待ちわびていたが、居間の縁側から見える彼の姿に気づき、慌てて玄関に向かった。
急いで突っ掛けを履いて、梅を眺めている毛利の前に慎治が駆けつけると、毛利は驚いた顔で目を見張った。
「慎ちゃん、だろ? いゃあ。大きくなったな~」
慎治も幼稚園の頃とはいえ、毛利のことはおぼろげながら記憶に残っている。
当時は毛利のおいちゃん、とタメ口を叩いていたものだが、同じ調子で話すわけにもいかず、かと言って敬語も水臭い。
どう反応していいのか分からず、慎治は、ただはにかんで微笑した。
「覚えてる?」
毛利の問いかけに、慎治は自分でも驚くほど甲高い声で応えた。
「もちろんです!」
優しい目で毛利は何度も頷いた。
「実際によく会っていたのは五歳くらいの頃だったからねぇ。だけど、その後も、君らのことはよく丈一郎君から聞かされてきたもんだよ。
それにしても…」
これまでのにこやかな表情を一変させ、毛利は眉を八の字にして同情を込めて語った。
「君らも大変なものを背負い込んじゃったなぁ…僕ら庶民から見れば贅沢な悩みかもしれないが。特に慎治君は長男に生まれたばかりに」
早く家に上がってお寛ぎ下さい、と言いたいところだったが、止まらない毛利の話を、しばらくは慎治もこわばった笑顔で聞くしかなかった。やがて、まるで七福神の恵比寿のように人懐っこい毛利の笑顔に接するうちに、慎治は、さきほどまで緊張していた自分が馬鹿らしくなった。
毛利のおいちゃんは全く変わっていない、あの時のままだ。そして、父の融通の利かない性格が少し柔らかくなったのも、こんな毛利の影響を受けたからに違いない、そう思った。
「さてと…」
一方的にまくし立てるように語っていた毛利だったが、彼は急に思い出したように慎治に向き直った。
「お父さんから、だいたい概略は聞いてるよ。自慢じゃないが、僕も社会科の教師だったし、郷土史についても一家言はあるつもりだ。なんの制約もあるわけではなし、とことん付き合おうと思ってね。それに、蔵の調査に立ち会えるなんて人生でまたとないチャンスだから、ねぇ!」
熱を帯びて語る毛利の姿は、人知れず、厄介なものを抱え込んでしまった、と落ち込んでいた慎治にとってはまさに救世主である。
「さぁ、ともあれ…」
毛利は背後にある蔵を振り返り、上から下へ、しげしげと眺めた。
「善は急げだ。さっそく、蔵を拝見しよう」
儀礼的に茶菓子などを客間に準備していた慎治は展開の速さにいささか面食らったが、素直に頷くと、きびすを返して母屋に蔵の鍵を取りに戻った。
慎治が母屋から持ち出した引き戸の鍵は長さが三十センチもある孫の手のような形状で、それを見た毛利は思わず感嘆の声をあげた。
小さな鍵穴から鍵の先端を器用に差し込み、かんぬきを持ち上げると、いとも簡単に漆喰の引き戸が開いた。
恐る恐る重い戸を引くと、室内からは長年積み上がったホコリとカビの匂いがつん、と一気に二人の鼻にまとわりついてくる。
蔵は二階建ての構造で、一階には二段の木棚に樽や桶などの役割を終えた民具が整然と並べられていた。
階段で二階に上がると、分厚い梁が巡らされた天井の下に六つの長持が手前から順序よく置かれ、奥の格子窓から差し込む柔らかい光が、ほこりの積もった床を暖かく照らしている。
毛利は、生活用品の鑑定や素性は後回しにし、大和家のルーツに関わるであろう古文書類が収められた二階の長持から先に調査することを慎治に申し出た。
祖母から慎治が聞いた話によると、長持は大和家に嫁いできた女性の年代順に並んでおり、鏡台や針箱などの嫁入り道具とともに、その時代の大和家にとって重要な品々が収められているとのことである。
まず、いちばん古いものから、と毛利は慎治に断りを入れ、奥の赤茶けた長持の木箱の蓋を持ち上げた。
==============================================
昼に蔵に入ってからというもの、二人は食事をすることさえも忘れて作業を続け、気がつけば時刻は夕方六時を回っていた。
慎治のお腹がなるのを聞きつけると、毛利は銀縁の眼鏡をずり下げて笑って侘びながら、今日はここまでにしておこう、と声をかけた。
板張りの床には新聞紙が敷かれ、その上に所狭しと分類され黄色い付せんがついた品々が並べられている。帯留めやかんざしなどの小物類から、日用品、什器とともに、一番手前には色違いの赤い付せんがついた書簡や古文書類が置かれていた。
最後に次回の調査のさわりだけでも、と、毛利が断りつつ、無造作にたばねられた和とじ本数冊を抜き取り、湿っ気た料紙をはがしながら慎重にめくり出した。すると、古文書特有の古紙の酸っぱいような匂いがたちまち辺り一面に広がった。
「慶長七年。筑前国穂波郡花瀬村田畠御検地帳、か。」
子供のように目を輝かせながら、毛利は次々と書を手に取り、斜め読みしている。そして、何冊かの確認を終えると、今日はこれで最後、と自ら宣言し、飴色に変色した一冊の和書の表紙を開いた。
が、数行読み進めるや、その手がふと止まり、その表情はみるみるうちにこわばっていった。
「…おぃおぃおぃ。こりゃ大変なものが出てきたぞ!」
毛利は驚愕したように目を丸くし、頬を紅潮させて声を裏返した。
「こりゃあ、、、庄屋日記じゃあ!」
慎治は、ひとり狂喜する毛利に戸惑いながらも訊ねた。
「他の本と何が違うんですか?」
毛利は興奮を隠せない様子だった。
「知ってるかい? 福岡の三大庄屋日記と呼ばれているものがあるんだけど、そのいずれもが県の重要文化財なんだ。庄屋の記録っていうのは公的なものと私的なものに分けられるけど、特に私的記録っていうのは当時の庶民の生活や世相が反映されていて、大変貴重なものなんだよ!」
毛利はそう言い終えると古文書の端を両手で握りしめたまま、うっとりと見つめている。
慎治は未だその価値を測りかねているのか、そういうものなんですかねぇ、と場違いな言葉を返した。
==============================================
終わるはずの調査だったが、毛利はもはや止まらなかった。発見した日記の解読により時間はさらに延び、慎治がもうこれくらいで、と促して作業を休止したのは午後八時を回る頃だった。
毛利は未だに発見の恍惚から抜け出せていないようであったが、急に何かを思い出したように我に返り、申し訳なさそうに慎治に問いかけた。
「慎治君、初対面の日にこんな申し出をして悪いんだが…」
恐る恐る、遠慮がちに毛利が切り出した。
「この日記、しばらく貸してくれないかな?」
夜の静寂の中、開け放たれた蔵の扉から漏れる白熱電球の灯りは、真っ暗な庭の地面をほのかに照らしていた。
大和家に隣接する花瀬八幡宮の社殿は遅い時間というのに元旦の準備のためだろうか、板戸の隙間から数人が忙しく立ち働いているのが見える。
昼間の暖かさが嘘のように冷え込んだ花瀬の澄み渡った夜空には、赤、黄、白、と、その色さえ分かるほどの満天の星が拡がっていた。